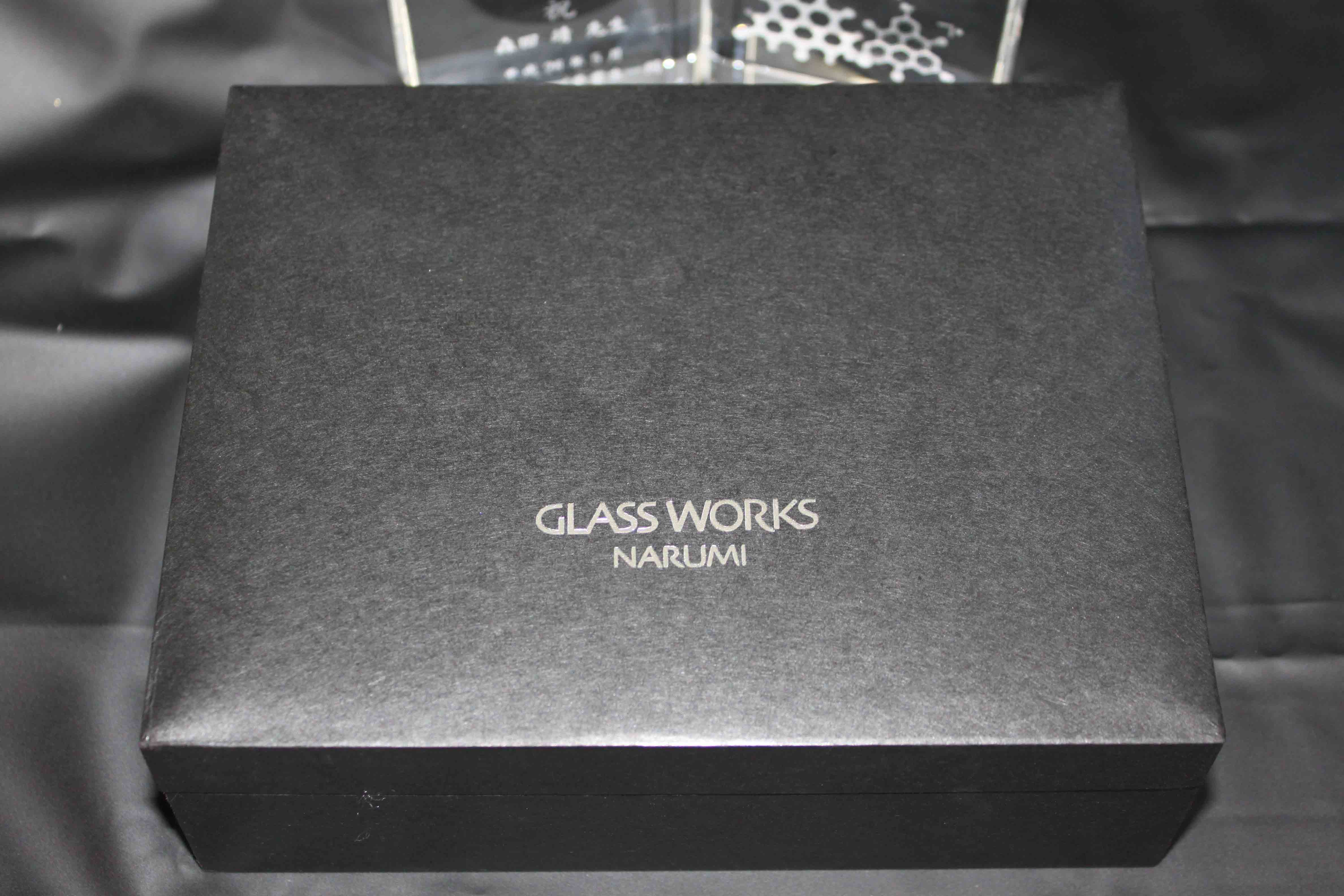トップ>過去のトピックス>2014年
2014年のトピックス
-
 月刊科学雑誌「Newton」2014年11月号(最新号)に、森田先生が実施しているJST元素戦略に関する特集記事が掲載されています。
月刊科学雑誌「Newton」2014年11月号(最新号)に、森田先生が実施しているJST元素戦略に関する特集記事が掲載されています。
「現代の錬金術 — 新材料をつくりだせ!」(p 120~133)(2014年9月26日発売)
JST CRESTホームページからこの記事が無料でダウンロード出来ます
(2014.10.17掲載、2015.1.7更新)
-
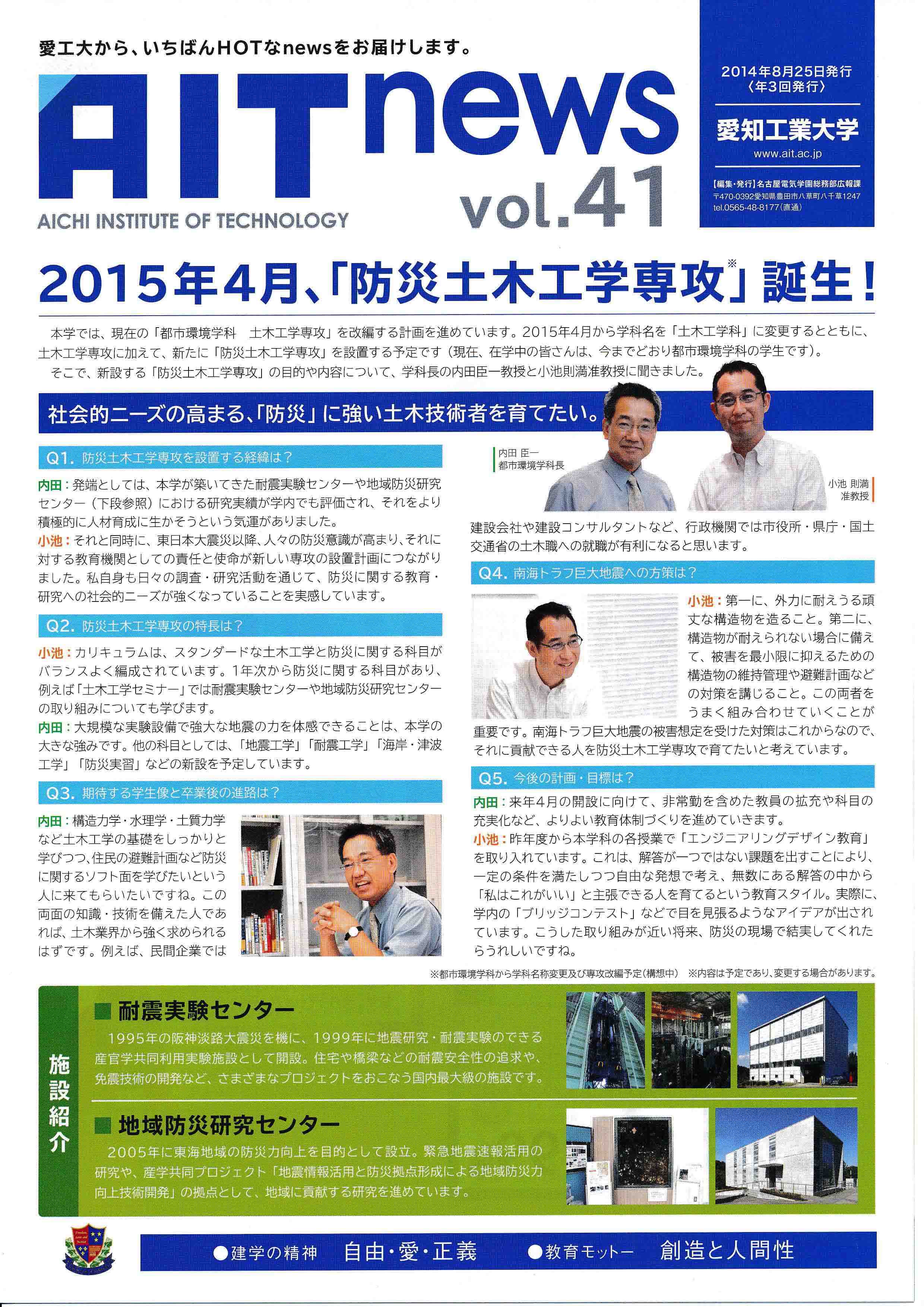 愛知工業大学のAITnewsに森田先生の記事が掲載されました。
愛知工業大学のAITnewsに森田先生の記事が掲載されました。
※掲載記事ナンバー AIT news2014.08.25/第41号
AITnewsの詳細はこちらから
(2014.10.1更新)
-
 『愛工大テクノフェア2014』
『愛工大テクノフェア2014』
来たる11月21日(金)に、愛知工業大学八草キャンパス1号館において『愛工大テクノフェア2014』が開催されます 当日は、『ポストリチウムイオン二次電池への挑戦:有機化合物が持つ多電子レドックス能を活用した分子スピン電池』と いうタイトルで森田教授の講演が予定されています。また、当研究室でも技術シーズ・ブース展示に参加します。是非ご来場ください
(2014.9.18更新)
-
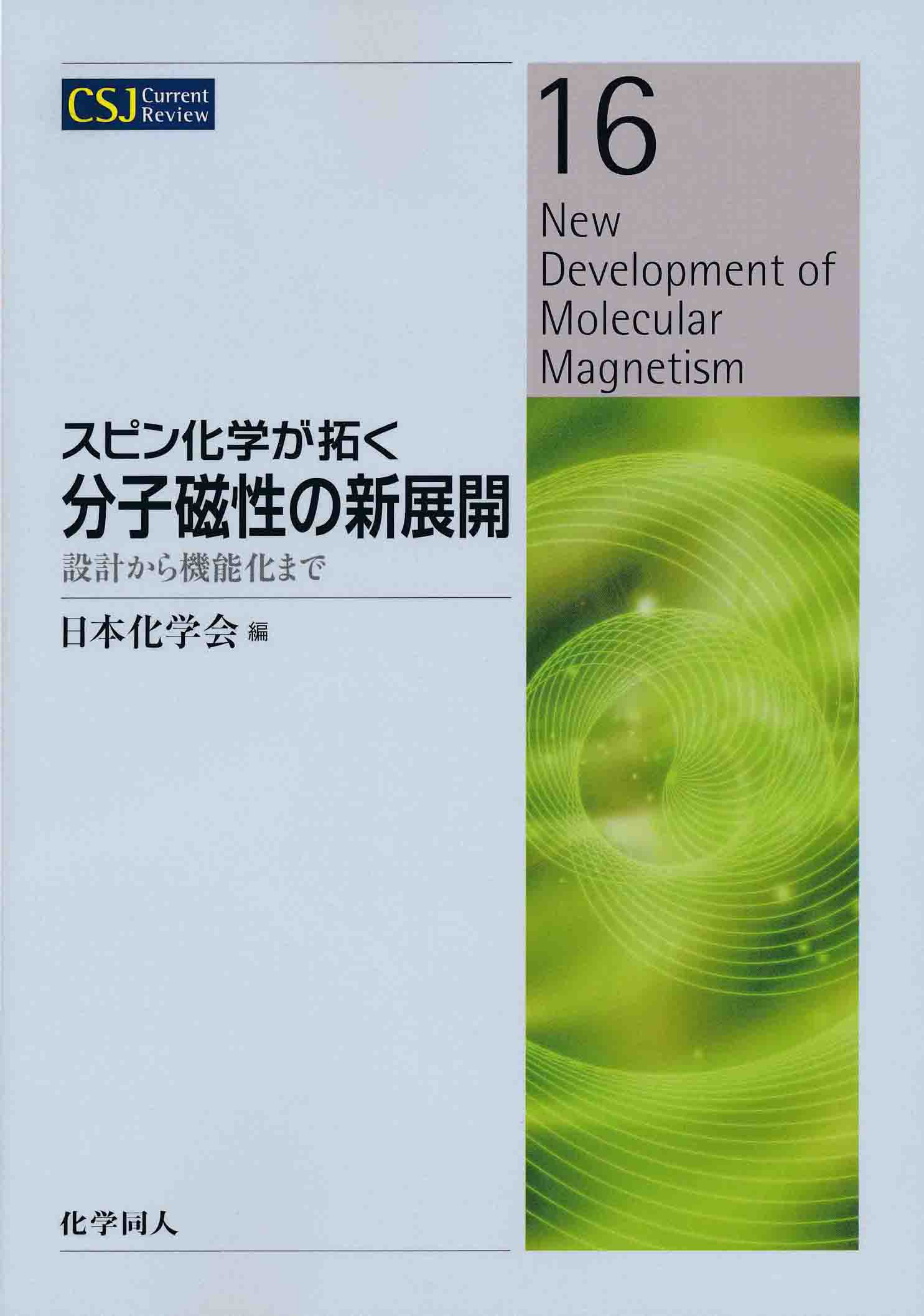 当研究グループで取り組んできた有機中性ラジカルや有機二次電池についての研究が、CSJカレントレビューに掲載されました。
当研究グループで取り組んできた有機中性ラジカルや有機二次電池についての研究が、CSJカレントレビューに掲載されました。
「縮合多環炭素中心型中性π-ラジカル・分子スピン電池」
西田辰介・森田 靖
CSJカレントレビュー 16「スピン化学が拓く分子磁性の新展開」Part II 研究最前線 4 章p 70-78
株式会社 化学同人 日本化学会編、2014 年 8 月 1 日出版
(2014.8.19更新)
-
 「錯体化学若手の会 夏の学校2014」に森田先生が講師として参加してきました(2014年8月1日から8月3日)
「錯体化学若手の会 夏の学校2014」に森田先生が講師として参加してきました(2014年8月1日から8月3日)
(2014.8.19更新)
-
 公益社団法人 電気化学会から発行されている学会誌「Electrochemistry」の特集「有機化合物を用いる二次電池の現状と将来展望」に、当研究グループで取り組んでいる有機二次電池についての研究が掲載されました。
公益社団法人 電気化学会から発行されている学会誌「Electrochemistry」の特集「有機化合物を用いる二次電池の現状と将来展望」に、当研究グループで取り組んでいる有機二次電池についての研究が掲載されました。
「ポストリチウムイオン二次電池への挑戦:有機化合物が持つ多電子レドックス能の活用」
森田 靖・西田辰介・朝倉典昭・信国浩文
Electrochemistry 2014, 82(8), 667–681
J-STAGE(本文の閲覧は電気化学会員限定)
(2014.8.7更新)
-
 株式会社工業通信から発行されている月刊技術雑誌「化学装置」(昭和 34 年 4 月創刊) に、当研究グループで取り組んでいる有機二次電池についての研究が掲載されました。
株式会社工業通信から発行されている月刊技術雑誌「化学装置」(昭和 34 年 4 月創刊) に、当研究グループで取り組んでいる有機二次電池についての研究が掲載されました。
「有機合成化学による二次電池用電極活物質の開発現状と展開」(出版社目次)
森田 靖・西田辰介
「化学装置」2014 年 8 月号 p 45-50
株式会社工業通信 化学装置編集部、2014 年 8 月 1 日出版
(2014.7.29更新)
-
 5月20日~21日に大阪大学テクノアライアンス棟にてCREST研究チームの報告会を行いました。
5月20日~21日に大阪大学テクノアライアンス棟にてCREST研究チームの報告会を行いました。
活発なディスカッションが行われ、有意義な時間となりました。
(2014.5.23)
-
 大阪大学基礎工学研究科の北川勝浩教授の研究グループと我々の共同研究により得られた研究成果が米国科学アカデミー紀要 (Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.) に本日掲載されました。我々が合成した位置選択的に重水素原子を導入したp-ターフェニル誘導体にペンタセンをドープした単結晶を用いた、レーザー光とマイクロ波による「光励起三重項状態の電子スピンを用いた動的核偏極法 (Triplet-Dynamic Nuclear Polarization)」についての研究結果であり、室温でのNMR信号を1万倍以上増大させることに世界で初めて成功しました。本研究成果は、極低温装置を使用せず低コストで、低温で分解してしまう生体物質や化学物質測定の高感度化を可能にし、化学分析に用いられるNMR分光や医療に用いられるMRI(核磁気共鳴画像)の飛躍的な高感度化に道を拓く画期的な研究成果です。
大阪大学基礎工学研究科の北川勝浩教授の研究グループと我々の共同研究により得られた研究成果が米国科学アカデミー紀要 (Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.) に本日掲載されました。我々が合成した位置選択的に重水素原子を導入したp-ターフェニル誘導体にペンタセンをドープした単結晶を用いた、レーザー光とマイクロ波による「光励起三重項状態の電子スピンを用いた動的核偏極法 (Triplet-Dynamic Nuclear Polarization)」についての研究結果であり、室温でのNMR信号を1万倍以上増大させることに世界で初めて成功しました。本研究成果は、極低温装置を使用せず低コストで、低温で分解してしまう生体物質や化学物質測定の高感度化を可能にし、化学分析に用いられるNMR分光や医療に用いられるMRI(核磁気共鳴画像)の飛躍的な高感度化に道を拓く画期的な研究成果です。
"Room Temperature Hyperpolarization of Nuclear Spins in Bulk"
Tateishi, K.; Negoro, M.; Nishida, S.; Kagawa, A.; Morita, Y.; Kitagawa, M.
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. in press (doi: 10.1073/pnas.1315778111)
新聞報道
MRIの感度1万倍以上に 阪大基礎工学研究科と阪大理学研究科(現在 愛知工業大学所属)が開発、微小ながん発見も可能。 量子物理学と有機化学の共同研究成果!
日本経済新聞電子版/日刊工業新聞電子版
Yahoo!ニュース版はこちら
大阪大学のホームページにも掲載されました。2014年5月13日 (火)
記事タイトル:世界初、室温でNMR信号を1万倍以上に増大
大阪大学基礎工学研究科システム創成専攻電子光科学領域の北川勝浩教授の研究グループは、試料を室温に保ったままNMR(核磁気共鳴)信号を1万倍以上大きくすることに世界で初めて成功しました。
愛知工業大学ホームページに掲載されました。2014年5月20日 (火)
記事タイトル:従来よりも何桁も室温で核磁気共鳴信号の強度を増大させる技術を開発! 詳しくはこちらをご覧ください
本研究は、科学研究費新学術領域「量子サイバネティクス」およびFIRST(内閣府 最先端研究開発支援プログラム)「量子情報処理プロジェクト」の支援のもと行われました。
(2014年5月13日掲載 2014.5.22更新)
-
 物性研究者にとって重要な事柄、正確な知識、新しい話題を提供する「固体物理(株式会社アグネ技術センター 出版)」の特集号「分子性固体の振物性・新機能」に、当グループで行ってきた電子スピン非局在型炭素中心中性ラジカルの基礎的な電子スピン物性と有機二次電池への応用に関する研究が掲載されました。
物性研究者にとって重要な事柄、正確な知識、新しい話題を提供する「固体物理(株式会社アグネ技術センター 出版)」の特集号「分子性固体の振物性・新機能」に、当グループで行ってきた電子スピン非局在型炭素中心中性ラジカルの基礎的な電子スピン物性と有機二次電池への応用に関する研究が掲載されました。
「電子スピン非局在型炭素中心中性ラジカルの電子スピン物性と有機2次電池への応用」(WEBページはこちら)
森田 靖・西田辰介
「固体物理」特集号「分子性固体の新物性・新機能」I. 物質開発・機能 2014年4月号・第49巻 第4号 p 23–34
株式会社アグネ技術センター、2014年4月15日出版
(2014.5.13更新)
-
 我々の2件の研究成果論文が、CSJ Journal Report Vol. 1 (2012-2014 First-quarter) の「Supramolecules」部門のHot Articles に選定されました。
我々の2件の研究成果論文が、CSJ Journal Report Vol. 1 (2012-2014 First-quarter) の「Supramolecules」部門のHot Articles に選定されました。
「CSJ Journal Report」は、日本化学会が発行する欧文誌「Bull. Chem. Soc. Jpn.」および「Chem. Lett.」に発表された最新の研究成果の中から、特に注目される論文を選出しそのグラフィカルアブストラクトを紹介する化学情報冊子です。
受賞論文:
"Cooperation of Hydrogen-Bond and Charge-Transfer Interactions in Molecular Complexes in the Solid State"
Morita, Y.; Murata, T.; Nakasuji, K.
Bull. Chem. Soc. Jpn. 2013, 86, 183–197 (Accounts)
"Development of Organic Conductors with Self-Assembled Architectures of Biomolecules: Synthesis and Crystal Structures of Nucleobase-Functionalized Tetrathiafulvalene Derivatives"
Murata, T.; Miyazaki, E.; Maki, S.; Umemoto, Y.; Ohmoto, M.; Nakasuji, K.; Morita, Y.
Bull. Chem. Soc. Jpn. 2012, 85, 995–1006
受賞日 : 2014年 3月26日
日本化学会 該当記事PDFはここからダウンロードできます
-
 多点相互作用部位を有する配位子TPHAP− とヨウ化亜鉛の自己集合によって溶媒の種類に応じ7種類もの配位性ネットワーク錯体が得られた。それぞれのネットワークは異なる相互作用様式を有する細孔を形成した。溶媒の違いによってもたらされたネットワークの多様性は弱い分子間相互作用のわずかな違いを認識するTPHAP− の多点相互作用能の効果を明確に示している。
多点相互作用部位を有する配位子TPHAP− とヨウ化亜鉛の自己集合によって溶媒の種類に応じ7種類もの配位性ネットワーク錯体が得られた。それぞれのネットワークは異なる相互作用様式を有する細孔を形成した。溶媒の違いによってもたらされたネットワークの多様性は弱い分子間相互作用のわずかな違いを認識するTPHAP− の多点相互作用能の効果を明確に示している。
"The Diversity of Zn(II) Coordination Networks Composed of Multi-Interactive Ligand TPHAP– via Weak Intermolecular Interaction"
Kojima, T.; Yamada, T.; Yakiyama, Y.; Ishikawa, E.; Morita, Y.; Ebihara, M.; Kawano, M.
CryEngCom in press (DOI: 10.1039/C3CE42382D, First published online 06 Jan 2014)
-
大阪大学 理学研究科 化学専攻 物性有機化学研究室(森田グループ)は、2014年3月31日をもちまして
愛知工業大学 工学部 応用化学科 物性有機合成化学研究室へ移転いたしました。
<所在地>
〒470-0392
愛知県豊田市八草町八千草1247
愛知工業大学 工学部 応用化学科 別館4階2410号室 森田研究室
愛知工業大学 工学部 応用化学科 別館2階2209号室 森田教授室
<連絡先>
電話:0565-48-8878(直通)
0565-48-8121(代表) 研究室内線:2209 教授室内線:2208
ファックス:0565-48−0076(共通)
愛知工業大学/交通アクセス
お近くへお越しの際は、是非お立ち寄りくださいませ。
(2014.4.11)
-
 テトラチアフルバレンを置換した6-オキソフェナレノキシル中性ラジカルの論文(S. Nishida, K. Fukui, Y. Morita Chem. Asian J. 2014, 9, 500-505, DOI: 10.1002/asia.201301188) について、
Chemistry An Asian Journal のカバーピクチャーに採用されました。
テトラチアフルバレンを置換した6-オキソフェナレノキシル中性ラジカルの論文(S. Nishida, K. Fukui, Y. Morita Chem. Asian J. 2014, 9, 500-505, DOI: 10.1002/asia.201301188) について、
Chemistry An Asian Journal のカバーピクチャーに採用されました。
溶媒分子との水素結合による6-オキソフェナレノキシルの温度依存CVと、それに伴う連続的なサーモクロミズム現象をドングリの葉の紅葉で表現しています。是非ご覧ください。
掲載ページはこちら
(2014.1.27)
-
 1月17日−18日にトヨタ自動車 三ヶ日研修所にてCREST「元素戦略を基軸とする物質・材料の革新的機能の創出」森田グループ チーム会議を行いました。
1月17日−18日にトヨタ自動車 三ヶ日研修所にてCREST「元素戦略を基軸とする物質・材料の革新的機能の創出」森田グループ チーム会議を行いました。
素晴らしい環境で、活発なディスカッションが行われ、とても有意義な時間となりました。今年も、これまで以上に邁進していきたいと思います。 どうぞよろしくお願いします。
CRESTホームページはこちら
(写真をクリックすると大きなサイズになります)
(2014.1.22)
最新のトピックスはこちら
過去のトピックス
2018年・
2017年・
2016年・
2015年・
2014年・
2013年・
2012年・
2011年・
2010年・
2009年以前
(c) Copyright 2009 Morita Group. All Rights Reserved.